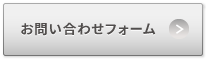高齢者の財産を守る生前対策としての「不動産名義の整理」とは、土地や建物の名義を今のうちに確認し、将来トラブルになりそうな点を整理しておくことを指します。不動産は現金と違って分けにくく、名義があいまいなままだと相続や売却の場面で大きな問題になりがちです。そのため、元気なうちに状況を把握し、必要な手当てをしておくことがとても大切になります。
まず確認したいのは、その不動産が本当に自分の単独名義になっているのか、それとも共有名義なのかという点です。親や配偶者と共有名義のままになっていたり、すでに亡くなった人の名義が残っていたりするケースも少なくありません。このような状態を放置していると、いざ売却しようとしたときや相続が発生したときに、関係者全員の同意が必要になり、話し合いがまとまらず手続きが進まなくなることがあります。生前に名義を整理しておけば、こうした混乱を避けやすくなります。
また、不動産の名義整理は、将来の相続対策にもつながります。誰にその不動産を引き継がせたいのかを考えたうえで、遺言書を作成したり、生前贈与や家族信託を組み合わせたりすることで、希望に沿った形で承継しやすくなります。特に、不動産が自宅しかない場合や、相続人が複数いる場合には、「誰が住み続けるのか」「売却するのか」といった点を事前に整理しておくことが重要です。
さらに、高齢になると認知症などで判断能力が低下する可能性もあります。その状態になると、不動産の売却や名義変更といった法律行為ができなくなり、結果として不動産が「動かせない財産」になってしまうことがあります。生前のうちに名義や方針を整えておくことは、こうしたリスクへの備えにもなります。
不動産名義の整理は、難しい手続きというよりも、「今どうなっているかを知ること」から始まります。登記簿を確認し、家族と話し合い、必要に応じて専門家に相談しながら少しずつ進めていけば大丈夫です。早めに手を付けておくことで、不動産という大きな財産を安心して守り、次の世代へスムーズにつなげることができます。